先日、今敏監督のアニメ映画『パプリカ』を観たことをきっかけに「今敏監督のほかの作品も観てみたい」と感じました。
そこで今回観てみたのが彼の長編映画監督デビュー作である『PERFECT BLUE』。
本作は『パプリカ』よりも前に制作された作品なのですが、この時からすでに独特な映像表現や心理描写の原点が感じられる一作でした。
空間が多層に折り重なる映像表現
アイドルから女優へと転身した主人公・未麻。
しかし事務所の利益を優先した過激な仕事(ヌード撮影や性暴力を受けるシーンのドラマ出演など)をこなすうちに、未麻は「アイドルだった自分」と「女優としての自分」の間で次第にアイデンティティを見失っていきます。
その混乱に追い打ちをかけるかのように、未麻のもとに爆弾が送りつけられたり、関係者が次々と殺害される事件が発生。
未麻の精神は限界へと追い詰められ、やがて今の自分を否定してくるアイドル時代の自分の幻影が見えるようになってきます。
そこからだんだんと現実と幻影の境界があいまいになっていき、物語そのものも〈現実・ドラマの撮影・妄想〉が複雑に交錯し始めます。
その構成は、今敏監督の代表作『パプリカ』と同じく、観る者にもどこまでが現実で、どこからが虚構なのか見失わせていきます。
特に妄想パートは未麻だけでなく他の人物の妄想も混ざっており、真相を理解する上でかなり混乱させられました。
観る者を惑わす、巧妙な演出
恥ずかしながら私には、演出や技法についての専門知識がまったくありません。
しかしそんな私でも、全編を通して同じ構図や動きを用いて、〈現実・ドラマの撮影・妄想〉が滑らかに切り替わる本作の演出は、かなり印象に残りました。
夢と虚構が曖昧になっていくストーリーにあの演出が加わる事によって、今自分が観ている映像は現実なのか、感覚的にも混乱させられます。
これもおそらく何かしらの有名な技法なのだろうと思い調べてみると、すぐにヒットしました。
こうした手法は一般的に「マッチカット」と呼ばれる編集技法に近いものらしく、今敏監督はそれをさらに発展させた独自の場面転換演出として使っているようです。
この独特の演出によって、作品の世界観に一層没入することができました。
インターネットにおける
心理描写や演出の解釈は複雑ですがストーリー自体は、
1.アイドルが女優へ転身
2.解釈違いを起こした犯人に精神的に追い詰められる
3.犯人との対峙
という分かりやすい流れで構成されていたので、意外と観やすい作品でした。
そしてその中でも特に気になったのが、未麻本人になりすましたネットストーカーが運営する未麻の日記というブログの存在。
まるで現代におけるインターネットトラブルを予見していたかのような設定で、今観ても強いリアリティと共感を覚えます。
この日記の存在が不気味に感じるのは、単にネットストーカーが彼女のプライバシーを侵しているからというだけではなく、未麻という人物がネット上で独り歩きし、本人よりも先に「架空の未麻」が出来上がっていたという部分が大きかったように思います。
画面の向こうでは誰かが勝手に彼女の感情を語り、世界へつながっている。
対して現実の未麻は精神的に追い詰められ、自分を失っていく。
この対比もまさに、現実のアイデンティティが虚構に飲み込まれ、曖昧になっていく構図になっていました。
しかし本作『PERFECT BLUE』が公開されたのは1998年。
当時はまだインターネットが一般に普及し始めたばかりの時代かと思われるのですが、この時からネットで自分を演出することの危うさを、ここまで緻密に描いていた事に驚かされます。
最後に
『パプリカ』から今敏監督の作品に興味を持ったことがきっかけで『PERFECT BLUE』を鑑賞したという経緯もあり、どちらの作品にも現実と虚構の境界が曖昧になっていく描写や、複数のアイデンティティを持つ女性主人公といった共通点が多くあったように感じました。
しかし妙な陽気さの中に恐怖を感じさせてくる『パプリカ』に対し『PERFECT BLUE』は登場人物の不安定な感情を表現しているせいか、よりダークで不穏な世界が広がっていたように感じます。
同じ「現実と虚構の境界」というモチーフを扱いながらも、方向性がまったく異なる感情へと導かれていきました。
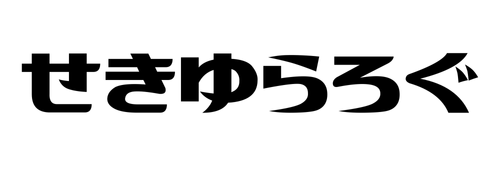



コメント